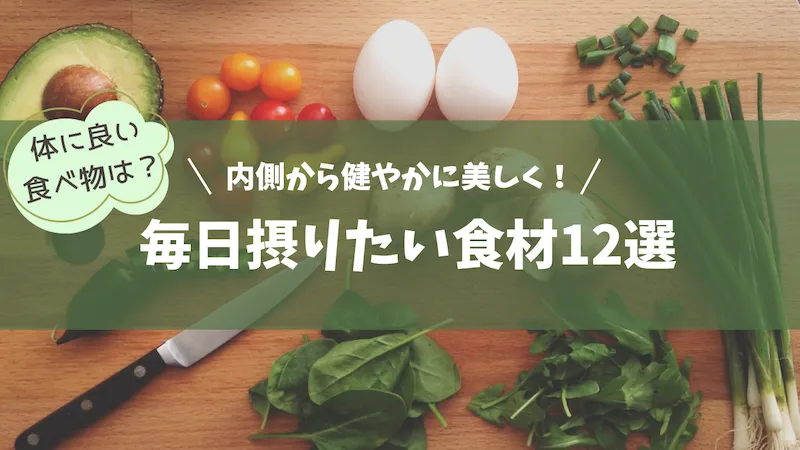「健康に良い」とされる食べ物は数多くありますが、本当に摂るべきものは何なのか、迷ったことはありませんか?
美容やダイエットにも役立ち、体調を整える効果が期待できる、毎日取り入れたい食材をご紹介します。
健康と美を支える、欠かせない栄養素とは?

「これを食べれば健康になれる」「この食品は避けるべき」といった情報があふれる中で、何を選ぶべきか悩むこともあるでしょう。特定の食材を意識して摂るあまり、かえって体調を崩してしまった…そんな経験のある人もいるかもしれません。
私たちが日々口にする食べ物は、エネルギー源となるだけでなく、心身のバランスを整える大切な役割を担っています。一つひとつの栄養素は単独で機能するのではなく、互いに影響し合いながら健康を支えているのです。
ここでは、美容や健康維持のために必要不可欠な栄養素をピックアップ。毎日の食事に取り入れたい食材を紹介する前に、まずは積極的に摂取したい栄養素について解説します。
体を動かすために欠かせない「炭水化物」
毎日の食事でしっかり摂りたい栄養素のひとつが「炭水化物」です。ご飯やパン、麺類に豊富に含まれており、体内でエネルギーとして活用される「糖質」と、消化されずに腸内環境を整える「食物繊維」の2種類に分けられます。
糖質は、体だけでなく脳の働きにも重要な役割を果たします。糖質が不足すると、集中力が続かなくなったり、イライラしやすくなったりすることも。脳は糖を蓄えることができないため、適量をこまめに補給することが大切です。
一方で、炭水化物の摂りすぎは体重増加の原因になることもありますが、極端に減らしすぎると疲れやすくなったり、思考力が低下したりする可能性があります。バランスを意識しながら、1日3回適量を取り入れることを心がけましょう。
体の基盤をつくる「タンパク質」
健康的な体づくりに欠かせないのが「タンパク質」です。筋肉だけでなく、肌や髪、爪などの細胞の材料となるため、毎食しっかり摂取することが推奨されます。
食事制限だけで体重を落とそうとすると、筋肉量が減少し、基礎代謝が下がることでかえって太りやすい体質になってしまうことも。効率よく代謝を維持するためにも、タンパク質を適量摂ることが重要です。
特に、朝食での摂取がポイント。夕食から翌朝までの時間が長いため、朝にタンパク質を補給しないと筋肉の分解が進みやすくなります。忙しい朝でも取り入れやすい卵、牛乳、ヨーグルトなどを常備しておくと便利です。
体の調子を整え、便秘対策にも役立つ「脂質」
脂質は、少量でも高いエネルギーを生み出す重要な栄養素です。使われなかった脂質は体内に蓄えられ、体温の維持や内臓の保護に貢献します。また、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収を助けたり、細胞膜やホルモンの構成成分としても機能します。
脂質の摂りすぎは体重増加につながりますが、不足するとエネルギー不足に陥ることも。さらに、脂質は腸の働きをスムーズにし、便秘を予防・改善する効果も期待できます。ダイエット中でも、必要な量を適度に摂取することが大切です。
体の働きをサポートする「ビタミン」
ビタミンは、体のさまざまな機能を正常に保つために不可欠な栄養素です。「脂溶性」と「水溶性」に分類され、全部で13種類が存在します。
人の体内では一部のビタミンしか作ることができないため、日々の食事からしっかり摂る必要があります。ビタミンは、炭水化物・タンパク質・脂質がエネルギーへと変わる際に欠かせない潤滑油のような存在。不足しやすい栄養素のため、意識的に摂取することが重要です。次に紹介する食品を活用しながら、効率よく取り入れましょう。
体の機能を維持する「ミネラル」
ミネラルは、エネルギーの生成を助け、体調を整える役割を持つ栄養素です。カルシウム・鉄・ナトリウムなど、体に必要な「必須ミネラル」は16種類存在し、それぞれが異なる働きをしています。
必須ミネラルは体内で作り出すことができないため、食事からの摂取が不可欠です。健康を維持するためにも、バランスよくミネラルを含む食品を取り入れることを心がけましょう。
毎日の食事に取り入れたい! 美容と健康を支える12の食材

食事のバランスが大切なのは分かっていても、具体的に何をどのくらい食べればよいか迷うことはありませんか? 健康維持や美容のために、積極的に摂りたい12の食材をご紹介します。最近あまり食べていないと感じるものがあれば、意識的に取り入れてみましょう(※1)。
なお、糖尿病や高血圧などで医師や管理栄養士の指導を受けている方は、指示に従った食事を心がけてください。
① 玄米・雑穀米
主食となるご飯やパン、麺類は、炭水化物を豊富に含み、体のエネルギー源として重要な役割を果たします。毎日の食事に欠かさず取り入れることが大切ですが、その中でも特におすすめなのが「玄米」や「雑穀米」です。
玄米は、もみ殻を取り除いた状態のお米で、白米に比べて栄養価が高いのが特徴です。例えば、ビタミンB1は約5倍、ビタミンEは約12倍も多く含まれており(※2)、食物繊維も豊富なため、腸内環境を整えて便秘の改善に役立ちます。
また、玄米は消化に時間がかかる分、腹持ちがよく、ダイエットにも適しています。ただし、胃腸が弱い方は、水を多めに加えて柔らかめに炊き、よく噛んで食べるのがおすすめです。
玄米の独特な食感が苦手な場合は、白米に雑穀を加えて炊くのも一案です。雑穀には、ひえ・あわ・アマランサス・キヌアなどが含まれており、ミネラルやビタミンB群、食物繊維が豊富。手軽に栄養バランスを向上させることができます。
1食あたりの適量は、軽く盛った茶碗1杯(約150g、1/4合)を目安にしましょう。
(※2)『一生役立つきちんとわかる栄養学』(飯田薫子・寺本あい監修/西東社)
② 青魚
肉を中心とした食事が多く、魚をあまり食べない方は、週に数回は青魚を取り入れるのがおすすめです。健康や美容をサポートする栄養素が豊富に含まれています。
青魚には、体に必要な必須アミノ酸をバランスよく含む良質なタンパク質が豊富です。また、青魚の大きな特徴は「DHA(ドコサヘキサエン酸)」や「EPA(エイコサペンタエン酸)」といった健康維持に役立つ脂肪酸が多く含まれていること。DHAは脳の働きをサポートし、EPAは血液をさらさらにする効果が期待できます。
さらに、ビタミンB群・ビタミンD・カルシウムなどの栄養素も含まれており、健康維持に役立ちます。ただし、魚の生臭さが気になる場合は、缶詰を活用すると手軽に摂取できます。
1食あたりの目安は、切り身なら1切れ(約80g)、アジやサンマなら1尾程度を目安にしましょう。
③ 脂肪の少ない赤身肉
牛肉・豚肉・鶏肉は、9種類の必須アミノ酸を含む良質なタンパク質源です。ただし、肉の種類や部位を選ぶことが重要。脂身の少ない赤身肉を意識して摂ると、効率よくタンパク質を補給できます。
牛肉や豚肉なら「もも」や「ヒレ」、鶏肉なら「ささみ」や「皮なしのむね肉」が低脂肪で高タンパクな部位。さらに、豚肉には疲労回復に役立つビタミンB1、牛肉の赤身には鉄分やミネラルが含まれています。鶏肉は消化が良く、皮を取り除くことでカロリーを約45%カットできるため、食事の量を調整しやすいのもポイントです(※3)。
1食あたりの適量は、80~100g(手のひらサイズで手の厚み程度)。牛・豚・鶏のどれでもよいので、毎日の食事に1回は取り入れるようにしましょう。
④ 卵
卵は、ビタミンCと食物繊維を除くほぼすべての栄養素を含む、非常に栄養価の高い食品です。特にタンパク質が豊富で、さまざまな料理に使いやすいのも魅力です。
卵の黄身と白身では含まれる成分が異なり、黄身にはタンパク質のほか、脂質、コレステロール、カルシウム、鉄分、亜鉛、ビタミンA・D・E・K・B群など、多くの栄養素が含まれています。食事の栄養バランスを整えるためにも、1日1個を目安に摂るとよいでしょう。
⑤ 大豆・大豆製品
「畑の肉」として知られる大豆は、タンパク質や良質な脂質を豊富に含み、栄養価の高い食品です。大豆に含まれる脂質の多くは、不飽和脂肪酸と呼ばれる健康的な油で、体に必要なビタミンやミネラル、食物繊維、イソフラボンも豊富に含まれています。健康維持のために、日々の食事に取り入れるのがおすすめです。
大豆を原料とする食品には、豆腐、納豆、豆乳、厚揚げ、おから、きなこなど、さまざまな種類があります。自分の好みに合うものを選び、無理なく続けられる形で摂取しましょう。
1食あたりの目安量は、豆腐なら約100g(1/3丁)、納豆なら1パック(40g)です。
⑥ 緑黄色野菜
健康を維持するためには、1日350g以上の野菜を摂ることが推奨されており、そのうち3分の1は緑黄色野菜が理想的とされています(※4)。この量は、生の野菜なら両手いっぱい(約120g)、調理した野菜なら小鉢1~2皿分に相当します。
緑黄色野菜には、小松菜、ほうれん草、ブロッコリー、にんじん、トマト、ピーマン、チンゲン菜、ニラ、アスパラガスなどがあります。これらの野菜には、ビタミンやミネラル、食物繊維に加え、抗酸化作用を持つ「フィトケミカル」も豊富に含まれているため、積極的に摂取しましょう。毎回の食事に、野菜を使った小鉢料理を1~2品取り入れるのが理想です。
⑦ 牛乳・乳製品
牛乳や乳製品には、タンパク質、カルシウム、ビタミンB2がたっぷり含まれており、毎日摂取するのが望ましい食品の一つです。特にカルシウムは吸収率が高く、不足しがちな栄養素を効率よく補うことができます。
牛乳が苦手な場合は、ヨーグルトで摂るのもおすすめです。ヨーグルトには乳酸菌が含まれており、腸内環境を整える働きがあります。消化吸収も良いため、胃腸が弱い方でも比較的取り入れやすい食品です。
1日の摂取目安は、牛乳なら200ml(コップ1杯)、ヨーグルトなら100g程度が適量とされています。
⑧ 果物
果物には、ビタミンCやカリウム、食物繊維など、体に必要な栄養素が豊富に含まれています。特にビタミンCは体内に蓄積できないため、野菜とともに果物からも意識的に摂取することが大切です。ビタミンCには抗酸化作用があり、肌の健康を守る働きもあります。
ビタミンCは加熱や空気に触れることで減少しやすいため、できるだけ新鮮な状態でそのまま食べるのがおすすめです。果物をジュースにして摂る場合は、市販品よりも手作りのものを選び、作ったら早めに飲むことで栄養を無駄なく取り入れられます。1日の摂取目安量は約200gです。
⑨ ナッツ類
アーモンド、くるみ、ごま、ピーナッツなどのナッツ類は、適量を摂ることで健康や美容に役立つ食品です。これらには、オレイン酸やリノール酸といった良質な脂質や、ビタミンEが豊富に含まれ、血管や肌の老化を防ぐのに役立ちます。さらに、アーモンドはカルシウムや鉄、ビタミンB2が多く、ピーナッツにはビタミンB群が豊富に含まれています。
ただし、ナッツ類はカロリーが高めなので、食べすぎには注意が必要です。目安として、ピーナッツなら1日10粒程度を摂ると良いでしょう。細かく刻んで野菜に混ぜたり、ピーナッツバターなどの加工品を活用することで、手軽に取り入れることができます。間食として食べるのもおすすめです。
⑩ 発酵食品
発酵食品は、日々の食事に取り入れたい食品の一つです。ヨーグルト、納豆、味噌、漬物、乳酸菌飲料などには、腸内環境を整える乳酸菌やビフィズス菌が含まれています。
腸内の善玉菌は、加齢や生活習慣の影響で減少しやすく、それに伴い腸の働きも低下しがちです。しかし、発酵食品を摂取することで、腸内の善玉菌を増やし、消化を助けたり免疫力を向上させたりする効果が期待できます。さらに、血中のコレステロールを抑える働きもあるため、健康維持のためにも積極的に摂りましょう。1日1回を目安に習慣化するのが理想的です。
⑪ オリーブオイル
日々の食生活に取り入れる油を選ぶなら、オリーブオイルがおすすめです。オレイン酸という良質な脂肪酸を多く含み、健康維持に役立つとされています。オレイン酸は、善玉コレステロールを維持しながら、悪玉コレステロールを抑える働きがあり、動脈硬化の予防にもつながります。
油は空気に触れると酸化が進むため、開封後はできるだけ早く使い切るようにしましょう。摂取量の目安は1日あたり大さじ1~2杯程度。体に良いからといって過剰に摂るとカロリーオーバーになりやすいので注意が必要です。サラダのドレッシングに使ったり、普段の料理の油をオリーブオイルに置き換えるなど、適度に取り入れましょう。
⑫ 緑茶
食事の合間や休憩時間に飲む機会の多い緑茶は、健康に良い成分を豊富に含む飲み物の一つです。特有の渋み成分であるカテキンには、強い抗酸化作用があり、体の免疫力を高める効果が期待できます。さらに、ビタミンCやカリウム、葉酸なども含まれており、美容や健康の維持にも役立ちます。
また、緑茶に含まれるアミノ酸の一種「テアニン」には、リラックス効果があるとされ、気分を落ち着けたいときにもぴったりの飲み物です。ただし、カフェインを含んでいるため、就寝前の摂取は控えめにし、夕方までに飲むようにすると良いでしょう。
控えめにしたい食べ物とは?

健康維持のために積極的に食べたい食品がある一方で、摂りすぎに注意したい食べ物もあります。特に、脂身の多い肉や高カロリーなお菓子は、適量を守って楽しむことが大切です。
肉はたんぱく質を豊富に含む栄養価の高い食品ですが、同時に「飽和脂肪酸」も多く含まれています。飽和脂肪酸は体内でエネルギー源となるものの、過剰に摂取すると中性脂肪やコレステロールの増加につながり、動脈硬化や肥満のリスクを高める要因になります。特に肉を多く食べる習慣がある人は、脂身の少ない部位を選び、青魚なども取り入れてバランスよく食べることを意識しましょう。
また、お菓子は気分転換やストレス解消にも役立ちますが、市販の洋菓子やスナック菓子には、炭水化物と脂質が多く含まれており、カロリーも高めです。完全に控える必要はありませんが、1日の摂取量を200kcal程度に抑えたり、栄養価の高い間食を選ぶ工夫が求められます。ヨーグルトや果物、ナッツ類などを取り入れると、不足しがちなビタミンやミネラルを補うことができます。
さらに、健康に良いとされる乳製品も過剰摂取には注意が必要です。牛乳やチーズ、ヨーグルトなどには飽和脂肪酸が含まれており、大量に摂ることで中性脂肪やコレステロールの増加につながる可能性があります。適量を守りながら、バランスの取れた食生活を心がけましょう。
毎日の食事に取り入れたいメニュー例

紹介した健康的な食品も、単独で食べるだけでは効率的に栄養を摂取することは難しいものです。そこで、朝・昼・夜のバランスの取れた食事例とポイントを紹介します。
朝食
1日の始まりにしっかり食事を摂ることで、エネルギー補給と代謝の向上が期待できます。
【メニュー例】
- 玄米または雑穀米
- 卵焼き
- ほうれん草のおひたし
- 豆腐とわかめの味噌汁
- りんご1/2個
【ポイント】
ダイエット中の方もそうでない方も、朝食を抜かずにしっかりたんぱく質を摂ることが大切です。夕食から朝食までの時間が長いため、体がエネルギー不足になりやすく、たんぱく質を補給しないと筋肉量の低下につながる可能性があります。太りにくい体を作るためにも、卵や牛乳、ヨーグルトなど、良質なたんぱく質を含む食品を取り入れ、栄養バランスの整った朝食を心がけましょう。
昼食
昼食は、活動的な午後を支えるためにしっかりとエネルギーを補給する時間です。外食でも、栄養バランスを意識して選ぶようにしましょう。
【メニュー例】
- 玄米または雑穀米
- しょうが焼き(豚もも肉使用)
- 野菜サラダ(レタス、きゅうり、トマト)
- ピーマンとにんじんのきんぴら
- 根菜がたっぷり入った味噌汁(大根、にんじん、さつまいも、こんにゃく、うす揚げ、ねぎ)
【ポイント】
定食スタイルでの昼食がおすすめですが、例えばスパゲティミートソースにサラダを添えるなど、単品メニューに副菜を加える方法でも問題ありません。特に、野菜が不足しがちなので、毎食必ず摂るように心がけましょう。
夕食
夕食では、引き続きたんぱく質を意識的に摂りましょう。また、遅い時間に食事を取らないことも、健康維持には重要です。
【メニュー例】
- 玄米または雑穀米
- あじの南蛮漬け(玉ねぎ、赤ピーマン)とブロッコリー、プチトマト
- ゴーヤチャンプルー(ゴーヤ、木綿豆腐、にんじん、豚もも肉、卵)
- お吸い物(しめじ、えのきたけ、生しいたけ、はんぺん)
【ポイント】
青魚は1日に1回は摂取するようにしましょう。生魚が苦手な方は、缶詰のサバなどを使って工夫するのもおすすめです。
間食
1日3食で摂りきれない栄養素を補うために、間食を有効活用しましょう。ヨーグルトやナッツ、果物などを間食に取り入れて、食事の合間に必要な栄養素を補う習慣を作りましょう。
毎日の食事で気をつけるべきポイント

「これさえ食べれば栄養バランスが完璧!」という食材は残念ながら存在しません。健康を維持するためには、さまざまな食材を適量に食べることが基本です。栄養素は単独では働かず、相互に作用して体に必要な役割を果たします。
栄養素を効率的に吸収し、活用するためには、バランスよく摂取することが重要です。多様な食材を取り入れた食事を楽しむことで、自然と栄養バランスが整います。
まとめ:毎日食べるべき食べ物で内側から健康をサポート!

日々摂るべき食べ物と、それを取り入れたメニューの例、健康と美容に必要な栄養素について紹介しました。毎日の食事は、単にお腹を満たすだけでなく、あなたの美と健康に直接関わっています。
「これを食べれば健康になる」「これを食べたら不健康になる」という特定の食材はありません。大切なのは、さまざまな食材をバランスよく食べることです。
自分自身のこともそうですが、家族のことを思うと、しっかりと栄養が豊富なものを与えたいと思いますよね。
そこで便利なのがこちらのBASE FOOD(ベースフード)。
今話題の完全栄養の主食※です。
主食をBASE FOODに変えるだけで、1食に必要な栄養素がすべてとれちゃいます。※
忙しい時に助かることはもちろんのこと、好き嫌いの多いお子様にも良いですよ。
パンだけではなく、パスタやクッキーもあります。
※栄養素等表示基準値に基づき、脂質・飽和脂肪酸・n-6系脂肪酸・炭水化物・ナトリウム・熱量を除いて、すべての栄養素で1日分の基準値の1/3以上を含む。
詳細はこちらから
自分の食事内容がわからないときは、まず食べているものを書き出してみましょう。足りていない栄養素や過剰に摂取しているものを見直すことで、よりバランスの良い食事に近づくことができます。
毎日必要な食べ物を取り入れて、内側から健康で美しい体作りを始めましょう!